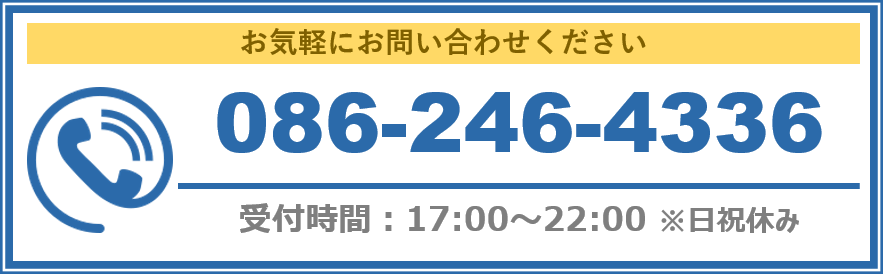今日の体重は 74.7kg 体脂肪率は 25.0% でした。
もうそろそろ春期講習の申し込み締め切りです。
がしかし、今年は例年になく申し込みが少ない。
学習に対する意欲と危機感がなくなってきているのか??
最近入塾した新中2になる生徒は計算も怪しい。と言うことで春期講習の受講を保護者にお願いしました。
すると「本人が行きたがらないので・・・でも話してみます。」とのお答え。
確かに本人が行きたがらないのに無理やり受講するのも良くないの
「親子げんかにならない程度に勧めてみてください」とお願いしておきました。
でも今のままでは2年生の1学期の数学は新しいことを学習しても計算が合わないので正解しない。
頑張ったのに点にならない。
面白くない。
嫌になる。
という負のスパイラルに陥ることになるかも・・・
なんとかしたいのですが、本人に自覚が無いと難しいですね。
昭和なら無理やりにでも受講させてましたが、今は令和なので・・・(笑)
今日教えてもらった良いお話は
綱引き理論というのがあります。
ご存知でしたでしょうか?
人間の力の出方を調べたもので
1対1の場合を100%とすると
2対2では、93%
3対3では、85%
8対8だと、49%
具体的に実験結果で表しますと
1人の時:63k(100%)
2人集団:118k(93%)
3人集団:160k(85%)
8人集団:248k(49%)
2対2だと63k+63kで126kになるはずが118k
8対8だと63k×8で500kあっていいのに半分以下の248k
と激減してしまうというものです。
また、面白いことに綱引きは、先頭の人が一番力を発揮しており、
後ろに行くほど減ってしまうのだそうです。
この綱引き理論は、別名「社会的手抜き」と呼ばれているそうで、
誰かがやってくれるだろうと思った結果です!
一流の経営者はこのことをよく理解されています。
京セラは、1973年の第一次石油ショックの時、ある工場で受注が激減し、
数カ月間も、通常の四割から三割程度しかないという事態になりました。
その時、創業社長の稲盛さんは、受注が半分なら半分の社員で動かす、
三分の一なら三分の一で動かすと、受注量に合わせた人間で動かす決断をし、
手の空いた人は工場美化運動の花壇をつくったり、
清掃やメンテナンスにあたるとともに、勉強会を開いたり、
新製品の開発を担当したりするというやり方をされました。
少ない注文を今までの人数でチンタラやったら、手抜き癖がついてしまう。
そんなことしていたら景気が回復した時にひどい目に遭うという判断からだそうです。
担当者の数が増えれば増えるほど、人ひとりのパフォーマンスは、だんだん小さくなる。
ひとりの人に、ひとつの仕事を依頼すると十分、能力を発揮していたのに
複数に依頼するとなかなか能力を発揮しない!というのは心理学の法則で、
無意識の依存心とも言われているそうです。
一方、火事場の馬鹿力などといわれるように
切羽詰まった時や人に頼ることが出来ない状況に追い込まれると
無意識の依存心から解放され、潜在能力が急に目覚め、
普段の何倍もの力を発揮するという事が起きます。
この時人間は飛躍的にレベルアップします。
ですから、自分の力を100%出そうと思うなら、
人を当てにしない!
誰かがやってくれるだろうではなく自分がまずやる。
自分一人でやる。自分だけはやる。
最大の敵は依頼心
綱引きは一番前に!